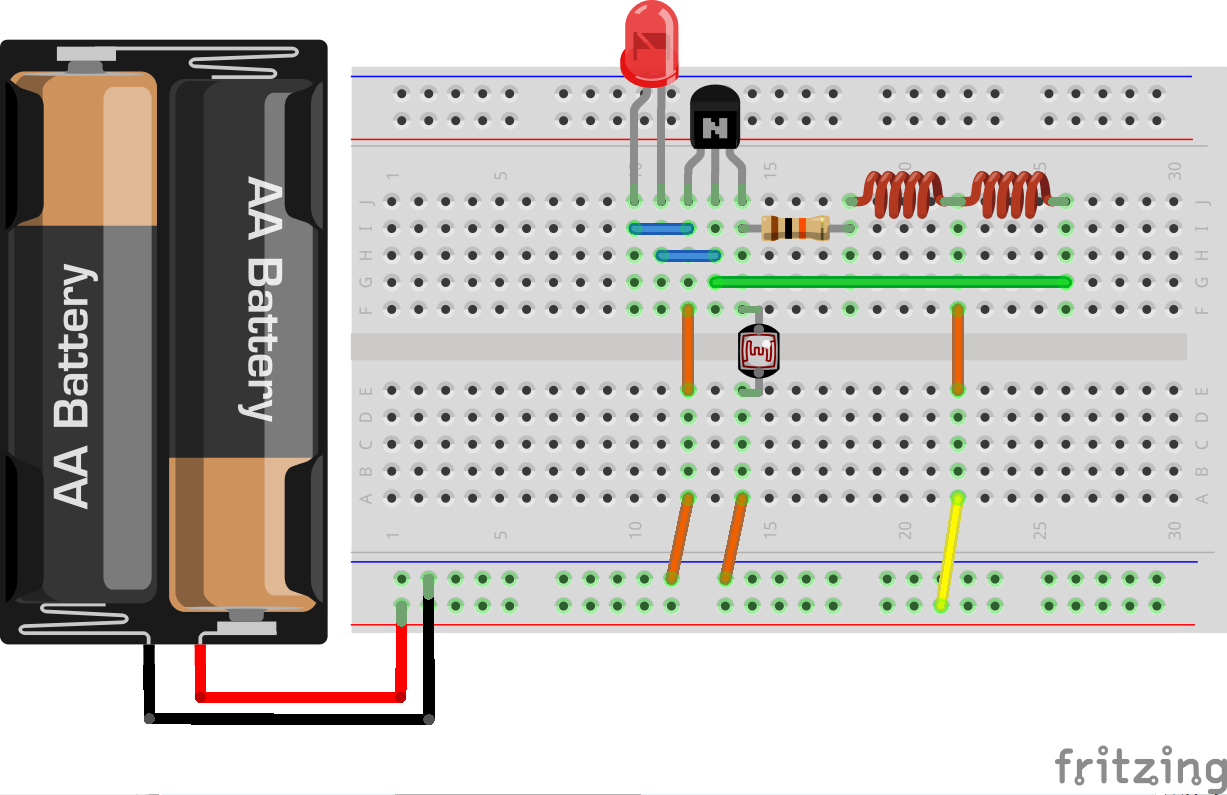手作り部品組合せ
コイルの組合せ回路
手作りコイルで作った回路では、スイッチを押して放した瞬間にピカっと光りました。スイッチをずっと連射すると、ピカピカと点滅していく様子がわかります。
それでは、この点滅の間隔がどんどん短くなるとどうなるでしょうか?
次の図のように回路を組んで、とてもとても短い間隔で点滅を繰り返すようにしてみます。
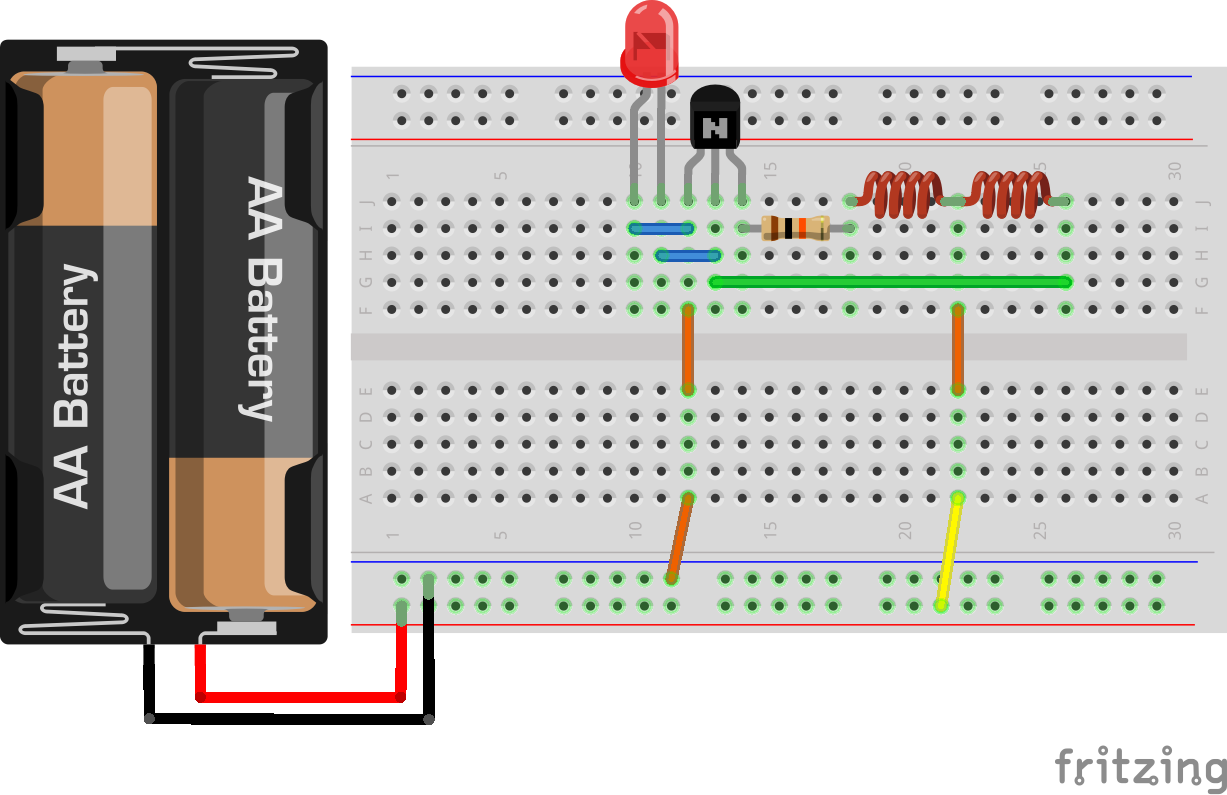 ※図では乾電池2本になっていますが、実際には1本です。
※図では乾電池2本になっていますが、実際には1本です。
LEDはずっと付きっぱなしになっているように見えます。 これは人間の目で認識できないほど早い間隔で点滅を繰り返すと、ずっと点灯しているように見える現象です。
では、本当に点滅しているのでしょうか? オシロスコープという計測器を使うと、実際に流れる電気を測ることができます。
LEDに流れる電圧をオシロスコープで計測すると、次のように波形にして見ることができます。
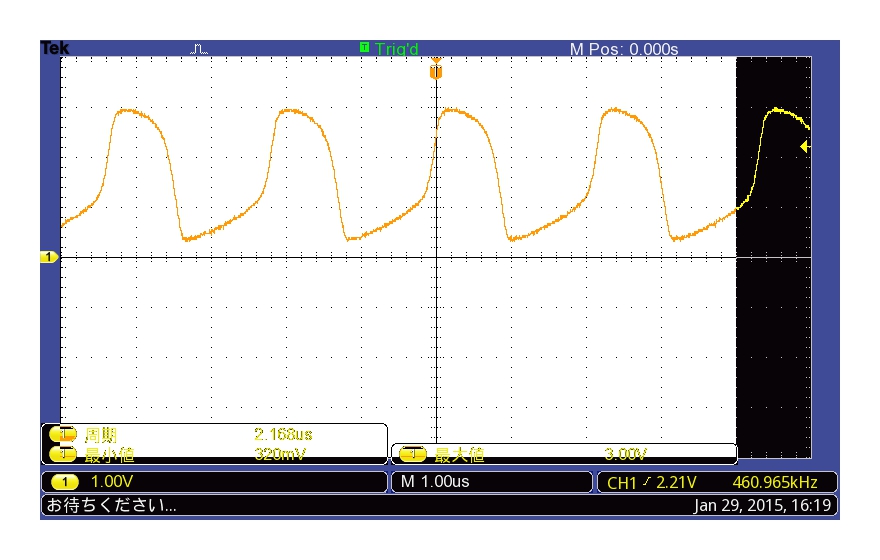 上のグラフは、x軸が電圧でひとマス1V、y軸が時間でひとマス1us(マイクロセカンド=100万分の1秒)です。
グラフの山の部分で点灯、谷の部分で消灯して、非常に早い間隔で点滅を繰り返していることがわかります。
上のグラフは、x軸が電圧でひとマス1V、y軸が時間でひとマス1us(マイクロセカンド=100万分の1秒)です。
グラフの山の部分で点灯、谷の部分で消灯して、非常に早い間隔で点滅を繰り返していることがわかります。
この波形のような状態を「発振」といい、電子回路では様々な場面で使われます。
ちなみに、この回路は「ジュールシーフ」といわれています。 使い古しの乾電池でも効率よく電気(電圧)を取り出してLEDを光らせることができます。
次の図のように、光センサー(CDSセル)を入れると、暗くなったら光るLEDライトになります。